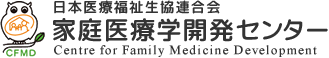家庭医の臨床的方法「Biopsychosocial アプローチ:The Basics」
ホーム » 家庭医の臨床的方法 » Biopsychosocial アプローチ
家庭医療における心理社会的次元の重要性
なぜ家庭医療の現場において、心理社会的問題が重視されるのか、その理由が理解できるよう、ケースを通じて解説しよう。
ケース1 受診理由
| 43歳男性 主訴は頭痛。A研修医が新患外来にて診察。時間的に余裕がなく、頭痛の性質と経過を聴取し、簡単な身体診察を行い、筋緊張性頭痛と診断。生活 指導とNSAIDを処方した。「あまり心配ないと思いますが、よくならなければいつでもどうぞ」と説明して診療を終えた。翌日その男性は別の大学病院を受診した。 |
なぜこの患者は翌日総合病院を受診したのだろうか?
実はこの男性は、半年前から職場が変わり、終日コンピュータのディスプレイを見る仕事になり、肩こり、後頭部の「じわっ」とする痛みを自覚するようになっ たが、仕事の影響だろうと考えてそれほど心配していなかった。ところが2週間前に同僚がくも膜下出血で緊急手術をうけるという事件があった。そのことを夕 食時妻に話したところ、「あなたの頭痛ってくも膜下出血じゃないの?お医者さんにみてもらったほうが、いいんじゃない?」といわれ、受診したのだった。し かし、めったにいかない病院ということで緊張してしまい、質問に「はい」「いいえ」と答えるのに精一杯で、大丈夫といわれて「やっぱり仕事のせいだよな」 と納得して帰ってきてしまった。妻にそのことを話すと、「ちゃんと検査してもらわないとだめよ。明日大学病院に一緒にいってあげるからMRIとかいう検査 をお願いしましょうよ」ということで、翌日別の総合病院を受診したのだった。
このケースが示しているのは、医学的診断治療に必要な情報である「主訴」となにを求めて受診したのかという「受診理由」が異なっていたということである。つまり、主訴=頭痛(Headache)、 受診理由=「くも膜下出血が心配」ということになる。
患者は何か心身の異常を感じたり、怪我をしたりすると、「これは医者にいったほうがいい」と決断し、受診する。むろん、あまりに症状が重かければ、「この 症状をなんとかしてほしい!」ということになり、主訴イコール受診理由になる。しかしプライマリ・ケア外来では、患者は自分でなんらかの決断をして受診に いたる。しかも、同じ程度の頭痛であっても、医師にかかるものもいれば、手持ちの鎮痛薬で様子をみるものもある。「医者にかかろう」と考えるなんらかのド ライブがかかる理由は様々である。重い病気ではないだろうかという不安、こういう時は医者にいったほうがいいという家族内の基準、うつ気分がありものごと を悪い方にとらえてしまう状態、ライフイベントがあった、会社で医者にかかるように指示された、などがあり得るが、それらはすべて心理社会的な内容であ る。つまり、なんらかの相談で外来を訪れる患者は、医学的な主訴という医学生物学的分析が必要な要因への対応とともに、受診理由という心理社会的要因に対 する対応が必要なのである。この診療の構造的特徴が、家庭医療において生物心理社会的なアプローチが強調される理由の一つである。
ケース2 見通し
| 15歳女性 昨夜より悪寒をともなう発熱出現。本日体温39度、倦怠感あり。迅速診断キットでA型インフルエンザと診断された。 |
この事例では明らかに発熱という苦痛を何とかして欲しいということが受診理由になっている。よって主訴イコール受診理由に近い。しかし、本人はいつから学 校に行けるようになるのか?今後ある受験に差し支えないか?といった心配事があるだろう。そのことが受診理由でなくても、そして診断が急性感染症であっても、心理社会的な問題への対応は必要であり、そしてそうした診療スタイルが、「なにかあったらまたこの医師に相談しよう」という継続性のキーとなる患者医 師関係を形作ることになる。
ケース3 生活機能
| 83歳女性 脳梗塞後遺症で左不全片麻痺がある。認知能はよく保たれているが、歩行時には杖が必要である。30代後半で現在住んでいる公営住宅の5階に入ったがエレベータがない。現在、外出時はどうしても介助が必要である。昨年までは散歩が好きで毎日出かけていたが、今年にはいって夫が亡くなってしま い、それ以来気力が衰えて、あまり外出しなくなってしまった。ケアマネージャの依頼で訪問診療が始まった。 |
このケースでは、歩行という人間の生活に必要な機能について考えてみよう。この患者は、身体的には杖で自力歩行可能な身体状態である。しかし、エレベータ のない公営住宅に住んでいるため歩行する環境が悪い。そして、夫の死後軽度のうつ状態になっていて、歩行する気力が減っている。つまり歩行するという機能 は、身体的、心理的、社会(環境)的に規定されている。言い換えるとこの患者への歩行に関する支援は、下肢筋力アップなどの身体医学的介入、うつ気分の改 善にむけた支持的治療、そして転居もふくめた環境の調整という生物心理社会的な介入により構成される。患者を実際の生活や労働のなかで支援し、QOLを向 上させるというスタンスもまた、家庭医療において生物心理社会的なアプローチが強調される理由となっている。
ケース4 複雑な問題
| 52歳男性 小さな製靴工場に、職人として28年勤務していたが、最近不景気と安い輸入品におされて仕事が減ってきており、給与支給も遅れがちで、リスト ラの対象になっていると気づいている。妻は収入がへっているためパートに出かけている。2人の高校生の息子がおり、これからの学費が心配である。最近いろ いろ考えてしまって、眠れないことが多く、体調がすぐれない。近くの病院で上部内視鏡検査をやったところ十二指腸潰瘍の診断となり治療が開始されたが、上 腹部不快感は取れず、医師からはうつ病といわれ抗うつ剤を開始された。そのころより、妻とは会話もほとんどなくなった。 |
このケースでは、消化性潰瘍、うつ状態、家族メンバー間の関係性の変化、仕事の状況とそれをとりまく社会状況など、身体的、心理的、社会的問題が複雑な フィードバック関係のもと、健康問題を形作っている。たんに消化性潰瘍に対する治療が、この男性の諸問題の解決あるいは安定化のキーになるかどうかは不確 実であるといえる。実際に労働や生活のコンテキストの中で診療する機会の多い家庭医は、こうした複雑な問題に対応することが多い。これは、生活から切り離 された状態で集中的にケアをする専門診療科による入院医療とは相当異なる状況であるといえよう。
生物心理社会モデルとは
1977年にEngeliiiがbiomedical model(生物医学モデル)に対比する疾患モデルとして、biopsychosocial model(生物心理社会モデル)を提唱した。これは人間の疾患(disease)あるいは病い(illness)を、病因⇒疾患という直線的な因果関係 ではなく、生物、心理、社会的な要因のシステムとして捉えようという提言である。
一人の人間を認識=記述するということは、システムの様々なレベルで可能である。たとえば、糖尿病を酵素などの生化学的プロセスで記述することができる し、また細胞や臓器レベルで生じる異常として記述もできる(図1)。さらに、自覚症状として口渇や視力低下などで記述すること、将来への不安など心理的に 記述することができる。また糖尿病があることで変化した家族内の役割を記述することもできるし、糖尿病治療と仕事の折り合いをどうつけているかを記述する こともできる。また各レベルはお互いに影響しあうフィードバックシステムを形成しているので、仕事上の問題が血中グルコースという分子レベルの変動に影響 をあたえうる。つまり糖尿病をもつその患者は生物、心理、社会的を含むシステムの異常として捉えなければ有効なケアには結びつかないだろうということであ る。この生物心理社会モデルは、人の疾患をどう捉えるかという認識の枠組みであるので、すべての医療の領域が検討すべきモデルであるともいえる。
図1 自然システムのヒエラルキーからみた糖尿病
生物環境 環境汚染
↑↓
社会・国家 糖尿病医療政策
↑↓
地域 医療機関の動き 仕事の変化
↑↓
家族 糖尿病ケアに必要な役割の再編成
↑↓
対人関係(二人の人間) 患者医師関係の変化
↑↓
個人の経験と行動 自覚症状、糖尿病への理解度、食行動
↑↓
神経系 免疫系や内分泌系への影響
↑↓
臓器システム 合併症の伸展
↑↓
組織 組織ダメージ
↑↓
細胞 細胞ダメージ
↑↓
分子 血糖上昇
近代以降において、疾患の主たる認識の枠組み=パラダイムとなった生物医学モデルにもとづく医学研究は、
- 疾患の原因はある特定の原因に還元できる(還 元主義)
- 物理化学的なメカニズムで生じている現象を説明でき、病因を排除したり、メカニズムの異常を正常化したりすれば疾患も治癒する(機械論)
という2つの前提に基づいている。そして生物医学モデルのパラダイムに基づく医学研究は、疾患の病態生理の解明、画期的な治療法の開発など極めて重要かつ有 用な成果を挙げてきた。このモデルにおいては、個々の患者は一般科学法則の適応例の一つとなり、他の症例と互換可能なものと認識される。従って、個々の患 者のユニークな人生、こころの問題、社会文化政治的問題、対人関係、家族や友人、医療者自身、患者自身の病いへの理解、患者自身にとっての病いの意味、治 療に対する患者の希望・価値観・選択といったことは全て捨象せざるを得ないのである。
近年、こうした特徴をもつ生物医学モデルが研究モデルにとどまらず、医療提供のモデルにも過度に影響を与えてきたことが問題になっており、生物医学モデル が現代医療の矛盾の構図の一端を担っているともいわれている。たとえば、現代医療にもっと必要なこととして、以下のような要素が挙げることができるだろう。
- 患者を人格・個人として尊重すること
- 対人関係を重視すること
- 効果的なコミュニケーションが大切なこと
- 医師の指示より,話し合いにもとづく意思決定や教育に焦点をあてるべきであること
- 疾患を治癒させることは,究極的にはよりよい人生を生き抜くことより重要とはいえないのではないかという疑問の尊重
そして、これらの要素と、先に述べた生物医学モデルが捨象する領域はプライマリ・ケアを担う家庭医がその仕事の中で重視する次元と完全に一致している。また、注目しておきたいのは、これらはすべて、医療倫理あるいはバイオエシックスの分野が取り扱う領域でもある。つまり、家庭医療と医療倫理は実はきわめて 近い関係にあり、共通の役割があるともいえる。
いずれにしても、最初にとりあげたケースをみれば、家庭医療においては、生物医学モデルのみではほとんど仕事にならないことに気づくのではないだろうか。 たとえば、自分で判断して来院した患者はかならず心理社会的なレベルの受診理由があるのであってみれば、家庭医は生物心理社会モデルのパラダイムですべて の患者に対応せざるを得ないのである。
生物心理社会モデルに基づく臨床アプローチ
生物心理社会モデルを基礎に、家庭医診療の構造分析を通して、現実的に適用可能な臨床的方法論にまで練り上げられたものが、McWhinneyらによる患 者中心の医療の方法(Patient centered clinical method)である。これは次章で解説する。この章では、Engelが在籍していたRochester大学の生物心理社会モデルの理論的実践的継承者た ちが提唱している臨床実践の枠組みiiiを、いくつかのキーとなるチェックポイントとともに紹介する。
1.患者の病いの物語と生活をとりまく状況を明らかにする。
医学的な病歴聴取にくわえて、患者が病いにかかわる経験、その時の思いをストーリーとして再構成する。また、普段の生活パターン、家族構成とその役割、仕事 の内容と様子、地域の状況(医療機関や福祉施設の状況など)も明らかにしていく。これは医師だけでなく、多職種で取り組み、多様な情報を集めることでより 豊かなものなるだろう。
チェックポイント
|
チェックポイント
2.生物心理社会的要因を統合する
1.のプロセスのなかで、この患者をケアしていく上で重要だと思われる患者の生物医学的問題(診断等)、心理的状態、社会的要因をピックアップし、その相互の関係性やフィードバックシステムを考察し、各次元の要因を統合する。
チェックポイント
|
3.ケアを行う際に各種関係の重要性を確認する
2.のプロセスの中で様々な「関係性」が浮かび上がってくる。患者ー医師関係に加えて、患者家族との関係、医師同士の関係、患者ーコメディカルー医師との 関係、地域の様々な機関との関係など、ケアにかかわる多種多様な関係があり、そうした関係性のなかでケアが行われると同時に、関係性そのものがケアの成否 をわけることが多い。さまざまな関係性がうまくいっているかどうかをつねにチェックし、その質を確保することが必要である。
チェックポイント
|
4.医師が自分自身を知ること
3.にのべたような関係がうまくいかない場合、それに対処するためには医師自身が自分の価値観や判断基準、好き嫌い、性格タイプ、体調などに気づく必要で ある。特に患者ー医師関係に問題があるとケアは大概うまくいかないので、この自己認識は大切である。生物医学モデルによる医療があるとしたら、おそらく医 師は観察者・操作者としてシステムの外にいることができる。しかし、生物心理社会モデルにおいては、医師はシステムの一部を形成しており、中立な立場でい ることができない。このことに自覚的になることが求められる。
チェックポイント
|
5.どの領域に焦点をあてて取り組むかを決める
生物心理社会的な要因とそのかかわりあいをあきらかにしたところで、すべての要因に同等に取り組むということは現実的ではない。実際には特に重要あるいは 優先度が高いと判断した問題に焦点を当てて取り組む必要がある。どこにまず取り組むのかということを決める際に、まずは生物医学的問題に焦点を当てていく というアプローチは、実際有効なことが多いものである。
チェックポイント
|
6.多次元的な治療を行う
生物心理社会的な介入は医師だけでなく、様々な領域の医療者がチームでとりくむことで、多面的に取り組むことが可能になる。各科専門医、看護師、理学・作 業療法士、薬剤師、ケースワーカーなどとチームを形成するだけでなく、施設の壁をこえた地域の保健福祉職などとの連携も重要で、特に複雑困難な事例につい ては「地域の力」を借りることも必要になる。
チェックポイント
|
まとめ
生物心理社会モデルは、家庭医療の実践における疾患・患者認識において有効な枠組みである。この枠組みにもとづく臨床的アプローチは、生物心理社会的要因 とそのからみあいを明らかにし、ケアを提供する側の関係性と自身への気づきを深め、問題の優先度の決定を行い、多職種チームによる多面的なケアを提供する ことである。
| 参考文献 i Engel G. The need for a new medical model: a challenge for bio- medicine. Science. 1977;196:129-136. ii Engel G. The clinical appplication of the biopsychosocial model. Am J Psychiatry. 1980;137:535-544. iii Frankel RM, Quill T. The Biopsychosocial Approach: Past, Present, Future. Rochester, NY: University of Rochester Press; 2003. |