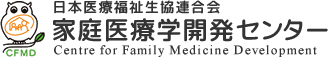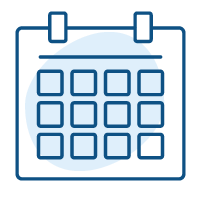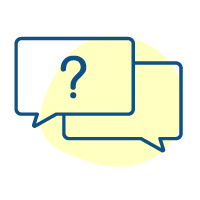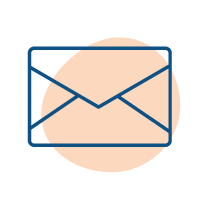家庭医療・プライマリヘルスケアを担う医師養成機関|地域における臨床研究・調査活動を全国的に行っています。
レジデンシー・近畿
家庭医療学開発センター(CFMD)総合診療専門研修プログラム・近畿
(略称:CFMDレジデンシー・近畿)
都市型・地域型診療所を拠点とし、自己主導型学習(Self-directed learning)による家庭医の研修を行います。研修の4年間で家庭医の基礎および一部の発展的な要素を学び、その後、生涯学び発展し続ける家庭医をめざします。レジデンシー修了後、日本専門医機構の総合診療専門医認定試験の受験資格が与えられます。
2013年度からはじまったCFMDの4つめのレジデンシーです。近畿で家庭医になる研修を受けたい方、ご質問などある方、見学ご希望の方など、お問い合わせください。
お知らせ
- 2025年10月21日 採用情報を追加
- 2025年 9月 4日 リレーインタビュー 第4回目 追加
- 2025年 8月25日 CFMD家庭医療学レジデンシー・近畿のミッション 追加

【CFMD家庭医療レジデンシー近畿/総合診療専攻医インタビュー】
一生学べる家庭医療!その基礎を学べる専門研修プログラム
研修の目標
- 医師としてEBMや予防医療を重視したよく訓練された臨床能力をもち、地域保健医療活動への参画を重視する視点を身につけ、都市部診療所において、非選択的な外来医療、在宅診療、保健予防活動をバランスよくおこなえる家庭医療専門医に必要なコンピテンスを獲得すること。
- 指導医として学習者中心の臨床教育を実施できるようになる。
- 研究者として臨床疫学、行動科学、地域指向性プライマリ・ケアに関する研究や実践の基礎的能力をもち、地域の健康問題に対して科学的な視点でアプローチできる。
- 生涯学習者として自己決定型学習を実施できる。常にアップ・トゥ・デイトな情報にアプローチでき、EBMを実施しつつ、反省的実践家としての家庭医らしい生涯学習をおこなうことができる。
- さまざまな地域プロジェクトにかかわり、リーダーシップを発揮することができる。
- 仲間として常に協同で学び、チームの一員としてその責任と役割をはたすことができる。
- 医療生協の発展に寄与するとともに、地域との様々な協同をすすめ、さらに世界の地域医療に貢献することができる。健康感・公平・正義などの価値観を涵養し、住民の主体形成への支援的かかわりができる。
カリキュラムの概要
研修期間:4年間
都市型診療所を拠点とする家庭医に求められるコンピテンスを勘案し、内科、老年医学と小児科(小児保健)、緩和ケアの比較的深い知識と技術の獲得を強調したローテーションスケジュールを組織する。また、整形外科領域や皮膚科領域などは、個別ローテートでは設定せず、教育診療所研修期間中に可能な形とする。また精神科領域については、行動科学、psychosocial medicineとして通年的に学ぶ課題として設定する。
ローテーションスケジュール例
| Horizontal Curriculum(標準型) | |
| 1年目 | 地域研修病院における総合内科研修 |
|---|---|
| 所属診療所へのワンデイ・パック(外来・往診) | |
| 2年目 | 小児研修 緩和ケア 僻地医療・救急医療 etc |
| 所属診療所へのワンデイ・パック(外来・往診) | |
| 3年目 | 教育診療所での外来・往診 |
| 通年エレクティブ(整形外科、皮膚科、ウィメンズヘルスなど) | |
| 4年目 | 教育診療所での外来・往診 |
| 総合診療研修 | |
研修施設
| 教育指定診療所 (4ヶ所) |
たじま医療生活協同組合 ろっぽう診療所 藤井高雄 医療生協かわち野生活協同組合 はなぞの生協診療所 石井大介 公益社団法人京都保険会 ふくちやま協立診療所 寺本敬一 尼崎医療生活協同組合 本田診療所 森敬良 |
|---|---|
| 主たる研修病院群 (7ヶ所) |
尼崎医療生協病院(総合診療Ⅱ、内科、小児科、整形外科/兵庫県尼崎市) 東大阪生協病院(神経内科、リハビリ/大阪府東大阪市) 耳原総合病院(総合診療Ⅱ、救急、外科、泌尿器科、緩和ケア科、整形外科、産婦人科、精神科/大阪府堺市) 兵庫県立尼崎総合医療センター(救急、小児科/兵庫県尼崎市) 沖縄県立宮古病院(総合診療Ⅱ、内科、救急、小児科/沖縄県宮古市) 京都協立病院(総合診療Ⅱ/京都府綾部市) 大阪旭こども病院(小児科/大阪市) |
カリキュラムの特徴
Horizontal Curriculum
地域に貢献できる家庭医となる観点から以下の内容を3年間のプログラムを通じて一貫して実施する。
- 診療所における継続外来・在宅診療(one-day back)
- レジデント・デイ(1ヶ月の振り返りとClinical Jazz)
- レジデント・セミナー(家庭医療のコアとなる領域の集中セミナー)
- プロジェクト・ワーク(プライマリ・ケア領域に関する研究プロジェクトを行う)
4年間教育指定診療所所属
所属は教育指定診療所とする。活動拠点はローテート研修先にかかわらず1カ所の教育指定診療所とし、家庭医のメンターをもつ。なお、プログラム管理は、医療福祉生協連 家庭医療学開発センターが行い、プログラム管理委員会を関連科の代表者で構成することにより、多くの法人にまたがった診療所基盤型のレジデンシーの構築を可能にしている。
質の高い形成的評価と総括的評価
- 日本家庭医療学会に準拠した研修目標に医療生協独自の研修目標を勘案した23領域におけるエントリーにより構築されたポートフォリオによる総括評価を行う。またこのポートフォリオ作成のモニタリングとサポートを定期的に実施する。
- 家庭医療専門医は広範囲の健康問題に関し網羅的な知識を必要とするため、シニア1、2学年終了時点でのMEQ(Modified Essay Question)を中心としたITE(In training Examination)を行う。
- レジデンシー修了後、日本プライマリ・ケア連合学会専門医認定試験を受験する。
メンタリングとサポートシステム
管理システムから独立したメンタリングによるサポート体制を家庭医療学開発センターが保障する。
- ミニ・フェローシップ
主としてシニア3年目でミニ・フェローシップ(通年的エレクティブ、週1単位)を選択できる。医学教育、行動科学、皮膚科、整形外科等 - 多彩な外部ファカルティー
家庭医療学センターが蓄積している外部のアドバイザーとのネットワークを活用する。臨床疫学、EBM、医学教育、生命統計学、医療政策、医療経済のスペシャリストに指導医陣に加わっていただくことにより、より質の高い研修を可能にしている。
プログラム概要
総合診療専門研修(日本専門医機構)
1.総合診療専門研修Ⅰ(外来診療・在宅医療中心)6ヶ月以上
2.総合診療専門研修 Ⅱ(病棟診療、救急診療中心)6ヶ月以上
(1.2.は合計で18ヶ月以上)
3.内科 6ヶ月(2024年度までは12か月)
4.小児科 3ヶ月
5.救急科 3ヶ月
(他に、へき地・過疎地域、離島、医療資源の乏しい地域での6ヶ月以上の研修)
☆新家庭医療専門医(日本プライマリ・ケア連合学会)と連動

研修施設(病院)
兵庫県立尼崎総合医療センター(救急、小児)兵庫県尼崎市
尼崎医療生協病院(内科、総合診療Ⅱ)兵庫県尼崎市
耳原総合病院(救急)大阪府堺市
東大阪生協病院(リハビリ、神経内科)大阪府東大阪市
京都協立病院(総合診療Ⅱ)京都府綾部市
※青字は必修科です。
2021年 4月~2022年 3月 内科(尼崎医療生協病院)
2022年 4月~2022年 9月 神経内科、リハビリ(東大阪生協病院)
2022年10月~2022年12月 小児科(尼崎医療生協病院)
2023年 1月~2023年 3月 救急(AGMC)
2023年 4月~2023年 9月 総合診療Ⅱ(尼崎医療生協病院)
2023年10月~2025年 3月 総合診療Ⅰ(本田診療所)
※日本プライマリ・ケア連合学会の
新・家庭医療専門医では、
・家庭医療Ⅰ(総合診療Ⅰ)
・家庭医療Ⅱ(総合診療Ⅱ)
を合わせて24か月以上必要
※専門医機構では合わせて18か月以上
↓
4年間の研修
↓
提出物、出願(5月中旬まで)
↓
(PC学会試験7月?)
専門医試験/面接試験10月?
↓
結果発表(翌1月?)
2023年 4月~2024年3月 内科(尼崎医療生協病院)
2024年 4月~2025年3月 総合診療Ⅱ、小児科、救急(宮古病院)
2025年 4月~2025年9月 総合診療Ⅱ(D病院)
2025年10月~2026年9月 総合診療Ⅰ(E診療所)
2026年10月~2027年3月 緩和ケア、整形、皮膚科、放射線科など(F病院)
2023年 4月~2024年3月 内科(尼崎医療生協病院)
2024年 4月~2025年3月 総合診療Ⅰ(本田診療所)
2025年 4月~2026年3月 総合診療専門研修Ⅱ、小児科、救急(G病院)
2026年 4月~2026年9月 総合診療Ⅱ(H病院)
2026年10月~2027年3月 総合診療、その他(未定)
・教育・研究、診療所開発により、地域の人々の健康状態の向上に資することが目的
・レジデンシーの運営(東京2006、東海2007、せとうち2010、近畿2013、東北2014、山陰2014)
・CFMDにおける家庭医像(非選択的外来診療と在宅医療おける生物医学知識と技術、癒し手Healerとして機能する、ヘルスシステムの構築者となる)
・世界で活躍できる人材を育成
レジデンシー近畿 研修の特徴
(ワンデイバック/マンスリーバックと診療所fix)
2.レジデント・デイ(1ヶ月の振り返りなど、月2回)
3.レジデント・セミナー(オンラインなど)
4.専攻医同士のサポート、専門医試験対策
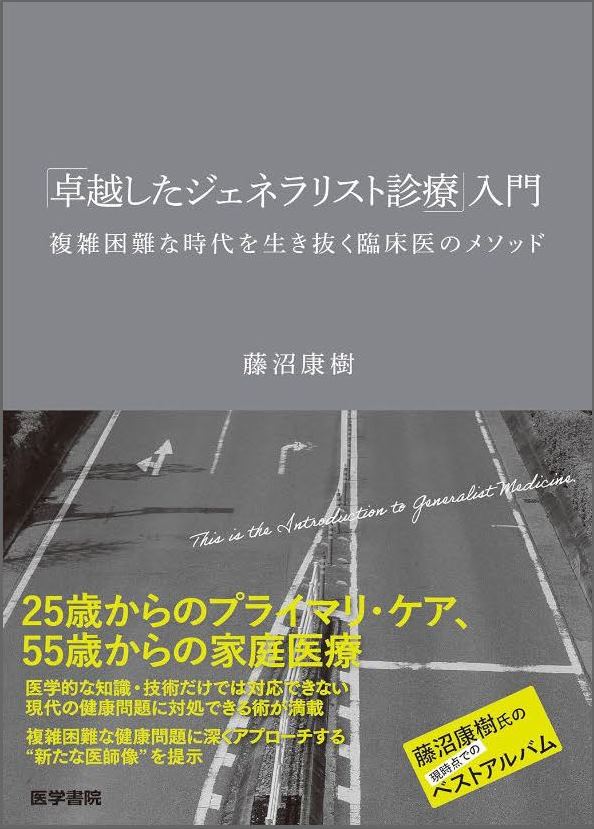
CFMD家庭医療レジデンシー近畿の修了生
2016年修了 X医師→在宅医療クリニック勤務
2017年修了 Y医師→クリニック所長として勤務
2019年修了 P医師→クリニック勤務、Q医師→クリニック勤務
2020年修了 R医師→クリニック院長として開業
2021年修了 S医師→クリニック勤務
2023年修了 T医師→病院勤務
2025年終了 U医師→クリニック勤務
※全国のCFMD修了生もクリニックや病院、大学などで活躍中
CFMDレジデンシー・近畿の詳細
総合診療専門研修Ⅰ:
外来診療、訪問診療、地域包括ケアを中心に行います。具体的には、急性期から慢性期、
予防や健康増進、緩和ケア、生活習慣病のコントロールや心理社会的問題への対応、認知
症を含む高齢者ケアなども含まれます。CFMD家庭医療レジデンシー近畿では教育診療所で
研修を行います。
総合診療専門研修Ⅱ:
病棟診療や外来診療を中心に行います。高齢者ケアや複数の健康問題を抱える患者への
対応、緩和ケアや退院支援、在宅患者の入院時対応などを経験します。外来では、救急外来
や初診外来を担当し、診断困難な患者への対応も含まれます。CFMDレジデンシー近畿では
尼崎医療生協病院、京都協立病院、沖縄県立宮古病院などで行います。
ご質問などある方、見学ご希望の方など、お問い合わせください。
メンバー紹介
指導医
詳細はこちら
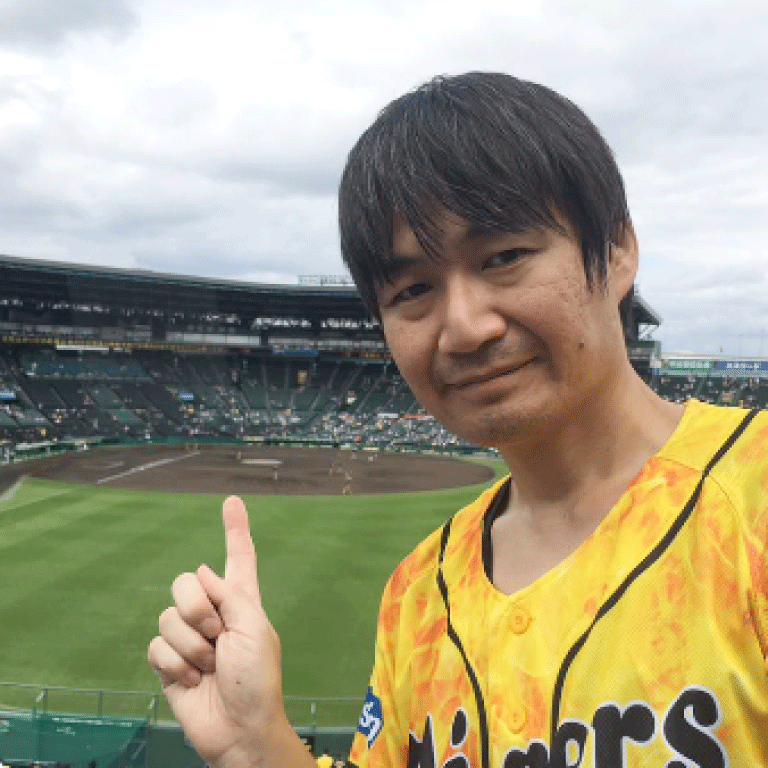 |
①名前:森 敬良 (もり たから) ②所属:尼崎医療生協 本田診療所 ③身分:所長 プログラム副責任者 プライマリ・ケア連合学会認定プライマリ・ケア認定医、指導医 ④コメント レジデンシー近畿では、専門医機構の総合診療専門医になるプログラムと、日本プライマリ・ケア連合学会の新家庭医療専門医になるプログラムの二つを運営しています。診療所が基幹施設のプログラムで、多くの病院とも連携しており、みなさんがなりたい家庭医像の実現のためにお役に立てると思います。一度見学に来ていただいて、楽しく研修している専攻医をぜひご覧ください おそらく日本で最も阪神甲子園球場に近いプログラムですので、プロ野球ファン、高校野球ファンの方にもおすすめです。阪神タイガースのナイターが18時から始まりますが、終業時間まで働いても十分に間に合います(ちなみに最寄り駅は阪神電車武庫川駅ですので、京セラドームも快速急行で14分です)。 |
|---|---|
 |
①名前:藤井 高雄(ふじい たかお) ②たじま医療生活協同組合 ろっぽう診療所 ③身分:プライマリ・ケア認定医、指導医 |
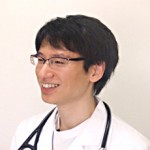 |
①名前:石井 大介(いしい だいすけ) ②所属:医療福祉生活協同組合おおさか はなぞの生協診療所 ③身分:所長 プログラム副責任者 プライマリ・ケア連合学会認定家庭医療専門医、指導医 ④コメント モノづくりとラグビーのまち東大阪で、地域住民の健康と暮らしに関わり続けています。 4年間通じて専攻医の先生と一緒に働く中で、お互いに学び成長を実感し合えることがこのプログラムの魅力だと感じています。地域で活躍している様々な職種の方と協働しながら地域医療に貢献できる楽しさをぜひ味わって下さい。総合診療・家庭医療の専門研修はもちろん、プライマリ・ケア分野のスキルアップやキャリアチェンジのための研修についてもフレキシブルに対応しています。ご興味のある方はぜひご相談ください。 |
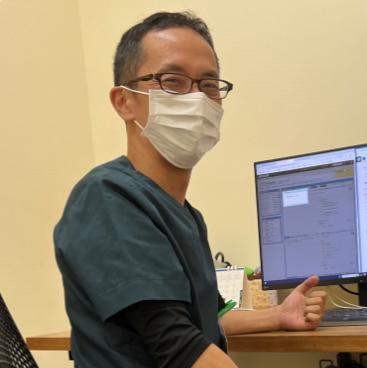 |
①名前:森永 太輔 ②所属:つむぎファミリークリニック ③身分:クリニックの院長をしています。 ④コメント: 名古屋市昭和区いりなかにある無床診療所です。 院長である私の専門は家庭医療で、家庭医療学の視点から外来診療、訪問診療、ワクチンなどの予防医療などを行なっています。 医学生の頃から、地域で働く地域住民の身近な医師になりたいと思っていました。それが何という専門家なのか当時は分からず、 恩師の勧めで「学生・研修医のための家庭医療学夏期セミナー」に参加してそれが家庭医と分かり、それ以来家庭医を目指して 研修してきました。 私が初期研修を行った時期はまだ初期臨床研修必修化前で、もちろん後期研修の制度もなかったのですが、すでに全国で活躍し ていた家庭医の先輩方の活躍に刺激を受けながら、家庭医として必要な知識やスキルや態度をジグソーパズルのピースを集める ように研修をしていきました。(今では家庭医療専門医は国際認定された後期研修プログラムとなっています) 時期的に家庭医療専門医制度ができる時期と重なり、専門医制度にのった医療生協家庭医療後期研修プログラムの家庭医療指導 都市部のプライマリ・ケアで家庭医が果たす役割はとても大きいと感じており、自分自身は家庭医になって本当に良かったと思っ |
 |
①名前:三宅 麻由(みやけ まゆ) ②所属:尼崎医療生協病院・本田診療所・潮江診療所 ③身分:プライマリ・ケア連合学会認定家庭医療専門医 日本専門医機構 総合診療専門医 ④コメント: 目の前の患者さんと向き合い、家庭医としてとても充実した毎日を過ごしています。家庭医になってよかったと思えるようなプログラムにしていき、専攻医とともに学び続けていきたいと思っています。 私は産婦人科領域も研修し、産婦人科で外来もしています。高校の学校医も担当したり、地域の小中学校に性教育講演を行ったりもしています。家庭医が活躍できるフィールドは幅広く、やりがいがあると思います。 初期研修から総合診療医になりたい人だけではなく、他科からの転向希望の方も受け入れます。 ぜひ一緒にCFMDレジデンシー近畿で研修しませんか? |
専攻医
詳細はこちら
 |
①名前:青木 岳喜(あおき たけゆき) ②所属:レジデンシー近畿(現在外回り中!) ③身分:専攻医 ④コメント: レジデンシー近畿の家庭医、総合診療医のプログラム研修中です。自分がやりたい研修をかなり自由度高く組めます。興味がある方まず見学からぜひ来てください。 |
|---|---|
 |
①名前:玉野 敦弘(たまの あつひろ) ②所属:尼崎医療生協 本田診療所 ③身分:専攻医 ④コメント: 初期研修期間の外来実習でお世話になった際、勤務されていた先生方の診療に感銘を受けました。来院した患者の笑顔、 Evidence-Based Medicine、地域を守る診療と、自分が「こうなりたい!」を思う家庭医療を実践できると感じてプログラムに参加させてもらいました。現在は医療を学び、楽しみながら研修を積んでいる最中です。 総合診療・家庭医療に興味がある方にはお勧めです。是非見学にお越しください。 |
 |
①名前:濵口 悠(はまぐち ひさし) ②所属:尼崎医療生協病院 潮江診療所 ③身分:専攻医 ④コメント: これまでは救急医学に興味があり、僻地の中核病院で救急に従事してきました。今後は内科、家庭医学を学び、急性期から慢性期、予防医学も含めて地域の患者さんの治療に携わりたいです。 当プログラムでは、診療所での経験、指導医の豊富なフィードバックや、月2回の振り返りがあり、腰を据えて学ぶことができると思い、レジデンシー近畿での研修を選びました。 興味のある方は是非見学にきてください。 (趣味はボルダリングなのでボルダリングの写真です) |
 |
①名前:徳山 美波(とくやま みなみ) ②所属:尼崎医療生協病院 本田診療所 ③身分:専攻医 ④コメント: 初期研修から尼崎医療生協病院と本田診療所でお世話になっていました。地域に根差した診療と手厚い指導、たくさんの修了生、ホワイトな働き方に惹かれて研修を決めました。家庭医に興味のある方は是非見学にお越しください。 |
修了生
詳細はこちら
 |
(登録医 OB) ①名前:平尾 悠介(ひらお ゆうすけ) ニックネーム 桜心亭喋賑喜〔往診亭聴診器〕 ②所属:musubiのクリニック ③身分:登録医終了、宴会部長、落語家見習い ④コメント レジデンシー近畿の研修を通じての学び 自らも楽しむこと 私達の仕事は状況に応じて流動的に変化していくため、常に上機嫌でいる事、相談できる余白をもつ事も大切な役割だと学びました。そこで笑いは日々必要と感じており、現在家庭医落語を修行中の日々です。見習いですが、一緒に見習って頂ける方募集中です。 |
|---|---|
 |
①名前:遠藤 浩(えんどう ひろし) ニックネーム:ヒロシ ②所属:尼崎医療生協 ナニワ診療所 ③身分:所長 ④コメント レジデンシー・近畿はそれほど大きな規模ではありませんが、仲間も多く、楽しくにぎやかに研修できます。自分は兵庫県出身で、島根や東京などで働いてましたが、兵庫に戻るときにレジデンシー・近畿があってよかったと思います。学んだ家庭医の技術を活かしながら、これからも生涯学習を続けて行き、地域のみなさんにお役に立ちたい所存です。 レジデンシー・近畿での研修や指導はとても魅力的だと思いますので家庭医になりたい人にお勧めしたいと思います。 |
 |
①名前:前田 亜里紗(まえだ ありさ) ②所属:尼崎医療生協 本田診療所 ③身分:プライマリ・ケア連合学会認定家庭医療専門医 ④コメント CFMDレジデンシー・近畿には、わきあいあいと一緒に勉強し、時に悩みを共有・相談でき、尊敬できる方々がたくさん在籍されています。家庭医として、また一人の人として成長していきたい方、是非CFMD近畿に遊びに来て下さい☆ |
 |
①名前:三浦 弓佳 ②所属: ③身分:プライマリ・ケア連合学会認定 家庭医療専門医、指導医 ④コメント: 私は2019年にCFMDレジデンシー・近畿での家庭医療の後期研修を修了しました。 後期研修中は、レジデント・デイの時間が確保されており、毎回じっくり振り返りを行うことができました。 当時、地域活動の一環で、銭湯に血圧測定に行っていたのもよい思い出です。 そのすべてが今の私の診療につながっています。 学びあい、成長し合う環境があるCFMDレジデンシー・近畿を皆様にぜひおすすめします! |
 |
①名前:東條 文明(とうじょう ふみあき) ②所属:医療法人青青会三愛クリニック ③身分:家庭医療専門医、プライマリケア専門医 プログラム修了生 ④コメント 実家が開業医で地域医療を志し、貧困や高齢化に興味を持つ中で都市型の家庭医療を学びたいと思い、医療生協と出会いました。 3年目は尼崎生協病院で急性期、地域包括ケアで病棟管理、4年目は尼崎生協病院でホスピスの緩和ケア、小児科、県立尼崎総合医療センターの救急など、5年目は東大阪のはなぞの生協診療所で外来、在宅、施設入居者の健康管理など幅広く学ばせてもらいました。診療所配属中もone day electiveとして週一日は皮膚科研修をさせていただきました。 現在は開業医として地域住民の健康に貢献すべく日々努力しております。 |
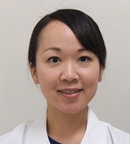 |
①名前:深澤 麻衣(ふかざわ まい) ②所属:尼崎医療生協 本田診療所・尼崎医療生協病院 ③身分:修了医 ④コメント 私がCFMDレジデンシー・近畿を選んだ1番の理由は、レジデント・デイで過ごす時間が私にとって非常に刺激のある学びの場になると思ったからです。月2回指導医の先生を交え、ここ1ヵ月間で学んだこと・経験したことを振り返って共有しています。興味のある方はまず、気軽に見学しに来てくださいね! |
 |
①名前:榮 仁規(さかえ ひとき) ②所属:尼崎医療生協病院 ③身分:プライマリ・ケア連合学会認定 家庭医療専門医、日本専門医機構 総合診療専門医 ④コメント: 昨年に家庭医療専門医、総合診療専門医を取得しました。4年間の研修期間の中で様々な患者様、ご家族と出会ってきましたが、病気だけではなくその患者様・ご家族の方々の想いや人生など様々な要因にも目を配り、1人1人と向き合いながら一緒になって診療に当たっていきたいと考えながら日々の研修に取り組んでいきました。中々日々上手くいかない事の方が多く挫けそうにもなりましたが、指導医の先生方の指導を始め、毎日外来後の振り返りやワンデイバック、月に1回の振り返りなど自分の疑問点や思ったことなどを丁寧に振り返る機会に恵まれたことは、とても良かったです。専門医となった今でも専攻医の振り返りに参加させて頂き、新たな発見もあり総合診療・家庭医療は奥が深く未だ未だ私自身も学ぶべき事が多いと実感しています。これからも日々の診療を通して患者様・ご家族ならびに地域の健康にも寄与できるように努力していきたいと考えております。是非一緒に学びましょう! |
 |
①名前:北村 紘之(きたむら ひろゆき) ②所属:尼崎医療生協病院 本田診療所 ③身分:専攻医 ④コメント: 地域に密着した医療を学びたくてレジデンシー・近畿での研修を選びました。いつでも気軽に相談できる方々がたくさんいて非常に恵まれた環境で研修させてもらっています。休日は趣味であるゴルフ、野球観戦をして過ごしており、公私共に充実した日々を送っています。興味のある方は一度是非見学にきてください! |
CFMD家庭医療学レジデンシー・近畿のミッション
詳細はこちら
家庭医・総合診療医の領域におけるリーダーとなる人材を養成とすることがCFMDのミッションです。家庭医療・総合診療をより高いレベルで実践し、教育・研究・リーダーシップについて深く学ぶために、本プログラム は研修年限を4年と設定しています。
各年次ごとの目標
〇1年次
患者の情報を過不足なく明確に指導医や関連職種に報告し、健康問題を迅速かつ正確に同定することを目標とします。主たる研修の場は内科研修となります。
〇2年次
診断や治療プロセスも標準的で患者を取り巻く背景も安定しているような比較的単純な健康問題に対して的確なマネジメントを提供することを目標とします。主たる研修の場は総合診療研修Ⅱとなります。
〇3・4年次
多疾患合併で診断や治療プロセスに困難さがあったり、患者を取り巻く背景も疾患に影響したりしているような複雑な健康問題に対しても的確なマネジメントを提供することができ、かつ指導できることを目標とします。主たる研修の場は、総合診療研修Iとなります。
総合診療専門医は日常遭遇する疾病と、傷害等に対する適切な初期対応と、必要に応じた継続的な診療を提供するだけでなく、地域のニーズを踏まえた疾病の予防、介護、看とりなど保健”医療・介護・福祉活動に取り組むことが求められますので、総合診療専門研修I及びⅡにおいては、地域ケアの学びを重点的に展開することとなります。
研修に関するQ&A
プログラムの内容と構成に関する質問
詳細はこちら
Q
レジデンシー近畿のプログラムで取得できるのは日本専門医機構の総合診療専門医だけですか?
Q
ダブルボードとサブスぺはどうなっていますか?
Q
僻地勤務は必須ですか?
Q
プログラムの自由度はどの程度自由ですか?指定されていく期間はどの程度ありますか?
Q
日本プライマリ・ケア連合学会の新・家庭医療専門医は取らず専門医機構の総合診療プログラムのみを3年で取ることは可能ですか?
Q
プログラムの4年間の研修期間は必須ですか?
Q
プログラムのローテーションはどのように組まれていますか?内科、外科、小児科など、各科の研修期間はどのくらいですか?
総合診療Ⅰ(※1) 外来診療、訪問診療、地域包括ケアを中心に行います。具体的には、急性期から慢性期、予防や健康増進、緩和ケア、生活習慣病のコントロールや心理社会的問題への対応、認知症を含む高齢者ケアなども含まれます。CFMD家庭医療レジデンシー近畿では教育診療所で研修を行います。
総合診療Ⅱ(※2) 病棟診療や外来診療を中心に行います。高齢者ケアや複数の健康問題を抱える患者への対応、緩和ケアや退院支援、在宅患者の入院時対応などを経験します。外来では、救急外来や初診外来を担当し、診断困難な患者への対応も含まれます。CFMDレジデンシー近畿では尼崎医療生協病院、京都協立病院、沖縄県立宮古病院などで行います。